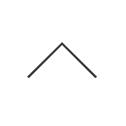シュリーマド・バーガヴァタム 第433話
更新日 : 2025.8.27
カテゴリー : シュリーマド・バーガヴァタム
サンカルシャナーヤ・ナマハ
第七巻 第13章
この章では、放棄者(サンニャーシ)のダルマ的な義務と、プラフラーダとダッタートレーヤ神との対話について解説します。
マハルシ・ナーラダは続けてこう述べています。
「真我探求に熟達した者は、非二元の真我を瞑想する間、この世界を完全に放棄すべきです。自身の肉体のみを所有すべきです。サンニャーシは村から村へと旅し、どの村にも一晩だけ滞在すべきです。いかなる欲望も持たずに、地上を放浪すべきです。
サンニャーシが身体を覆う必要がある場合は、腰布(コウピナ)のみを身に着けるべきです。彼は杖(ダンダ)、数珠(ジャパマーラー)、その他彼の人生の段階に関係する物のみを所持して、あるいは保持すべきです。言い換えれば、サンニャーシの段階を受け入れる際に放棄した、世俗に結びついた他のいかなる物も所持すべきではありません。
彼は施し(ビクシャ)のみによって生きるべきです。真我の至福に完全に浸り、自身の生を他のいかなる生類にも決して依存すべきではありません。すべての生類の幸福を確保しつつ、たった一人で、場所から場所をさまよい歩くのです。
欲望が完全に消失したサンニャーシは、究極の目的、すなわち至高主ナーラーヤナを得ることのみに集中すべきです。真我は時間を超えた存在であり、時間こそがすべての原因と結果(カーリヤ・カーラナ)の不可欠な前提条件であるが、その原因と結果を超えたものです。サンニャーシは、真我の内に全世界を知覚できる必要があります。
彼は内なる真我の中に万物を思い描くべきです。そして、そのような真我は至高主に属し、この万物全体のすべての生類に遍在していると信じるべきです。原因と結果という形で存在するこの全世界を、非二元的な至高主の内に思い描くべきです。言い換えれば、世界は真我の上に重ね合わされていることを理解すべきです。
目覚めと睡眠の境界、すなわち目覚めの時と就寝時において、真我に立脚したサンニャーシは真我探求を行うべきです。これらの節目において、束縛と解放はどちらも幻想であり、それらは本質的に真我に属するものではないことに気づくことができます。
「私はこの宇宙のあらゆるものと無関係である。これらの喜びや悲しみは私とは無関係である。それらはこの感覚器官にのみ属するのだ」。この認識をもって、サンニャーシは至高主に瞑想すべきです。真我は本質的に束縛されていないので、解放の問題は生じないことを理解すべきです。
真我はどのようにして束縛された対象となり得るのでしょうか?静止したまま、さまようことはありません。どのようにして解放を得るのでしょうか?感覚器官と完全に結びつき、自らを感覚器官であると信じている無知な人が解放を求めます。これらの感覚器官を超えた真我は、束縛されることがないため、解放を得ることができません。
至高主は一体どこにおられるのでしょうか?主はあなたの中におられます。しかし、主はあなたから独立した存在を維持しています。素晴らしいことではありませんか?主の存在なしには感覚器官さえも動かないと言われるのも無理はありません。このことから、主が動いていると断言できますか?いいえ。感覚器官は動きますが、主は感覚器官とは別の存在を維持しています。したがって、感覚器官は主の部分的な化身です。これらの感覚器官は破壊されます。しかし、主は非二元です。したがって、非二元である真我は解放されることはできません。遍在するものが、どうやってある場所から別の場所へ移動できるのでしょうか?どのようにして天界に到達できるのでしょうか?どのようにして地獄に到達できるのでしょうか?それは何にも触れられていないのです。
これらは、感覚器官と結びついた知性の想像上の創造物です。そのような知性は決して解放されることはありません。各器官は、それぞれの主宰神に捧げられるべきです。手、足、耳、目、そして生命力さえも、それぞれの主宰神に捧げられたとき、解放されるべきものは何かあるのでしょうか?何もありません。それゆえ、ヴェーダーンタは、真我は束縛されることも、解放されることもないと断言しています。
「この粗大な肉体はいつかは必ず滅び、寿命も不確定であるように、サンニャーシは長寿も死も称賛することはできません。死がすぐそこまで迫っていることに興奮することも、生きていることに喜びを感じることもできません。サンニャーシは、すべての生類の生と死を司る時間(カーラ)だけを熱心に観察すべきです。
音楽、舞踏、その他真我と無関係な芸術には一切関心を持つべきではありません。そのようなプログラムに参加することさえ望んではなりません。未来を予言をしたり、金銭のために働いたり、ビジネスに従事したりして生計を立てることも固く禁じられています。議論、反論、討論から完全に距離を置くべきです。シヴァ派、ヴィシュヌ派、その他のいかなる慣習にも傾倒すべきではありません。信奉者集団を持つべきではありません。無駄な書物を読むべきではありません。ここで理解すべきことは、ヴェーダーンタに関する書物以外では、占星術や真我と無関係なその他の科学に関する書物には近づかないようにすることです。そのような無駄な主題を教えるべきではありません。ムットや関連機関の設立に注力すべきではありません。
サンニャーサ・アーシュラマのこれらの厳格な規律は、至高の聖者(ヤティ)が一体感を持ち、至高主があらゆる場所に遍在していると見なす者にとっては必須ではありません。あらゆる外的な象徴に心を奪われることなく、サンニャーシは真我にしっかりと立脚します。そのようなマハトマは、外的な象徴を受け入れることも拒絶することも自由にできます。
ヤティは、自らの究極の目的が主と一つになることであると明確に理解しています。それでもなお、彼は自らの揺るぎない精神の状態を示す象徴的な外見を身につけません。たとえ完全な心の制御能力を有していても、人々の前では狂人か無知な子どものように振る舞うべきです。たとえ最高の学者であっても、愚か者のように振る舞うべきです。
この文脈において、マハトマは非常に古い物語を語ります。幾億年も昔、プラフラーダ皇帝とダッタートレーヤ神の間でこのテーマに関する議論がありました。ダッタートレーヤ・マハルシは「アジャガラ・ヴルッティ」と呼ばれる苦行を行っていました。それは、まるでニシキヘビのように、自分に与えられた食物だけを摂取するというものでした。彼はサヒヤ山近くのカーヴェーリ川の岸辺の裸地に横たわっていました。
アドークシャジャーヤ・ナマハ
第434話へ続く