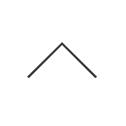バガヴァット・ギーター 第2章14~16節
更新日 : 2025.8.13
カテゴリー :
この体を離れた後、同じ魂は別の体を得ます。これを理解する賢者は惑わされていません。
「魂は永遠であると知っているので、魂が滅びる可能性があると惑わされることはありません。しかし、暑さ、寒さ、喜び、悲しみの経験、そして幸福から離れる悲しみとその悲しみと一つになってしまうことには惑わされてしまいます。」
アルジュナが「私は不死の真我を悲しんでいるのではありません。死んでしまう体を悲しんでいるのです」と尋ねると仮定して、クリシュナは言います。
mātrāsparśās tu kauntēya śītōṣṇa sukhaduḥkhadāḥ
āgamāpāyinō ’nityāḥ taṁstitikṣasva bhārataǁ 14 ǁ
暑さ、寒さ、喜び、悲しみの経験は、感覚が関連する対象に出会ったときに現れます。経験はつかの間で永続しない。耐えるのだ。
「マートラ」は感覚器官を指します。音、匂いなどは感覚知覚です。感覚器官とそれに関連する感覚知覚との接触は「マートラ・スパルシャ」です。この接触により、熱、寒さ、喜び、悲しみが生じます。
5つの動作器官は、発声、手、足、性器、肛門です。5つの知覚器官は、皮膚、目、耳、鼻、舌です。
寒さと熱は、時には幸福をもたらし、時には悲しみをもたらします。それとは違って喜びと悲しみは変わりません。そのため、彼は特に熱と寒さとは別に言及しています。
感覚と物体の接触 (マートラ・スパルシャ) によって生じるこれらの経験は、つかの間で永続しません。忍耐するのだ。
表面的には、この説明はアルジュナの質問とは無関係であるように見えます。しかし、クリシュナは、肉体は無常であると直接言う代わりに、感覚、それに関連する対象、そしてその結果生じる経験はすべて無常であると言います。
それらが消滅すると何が残るでしょうか? 何も残りません。これは、肉体は無常であると言っていることになります。シュリークリシュナはこのように巧妙に説明しました。
「クリシュナ、私はそれらが自ら現れ、つかの間のものであることに同意します。しかし、なぜ私たちはそれに耐えなければならないのですか?耐えることで何が得られるのですか?』アルジュナがこの質問をするかもしれないと仮定して、クリシュナは言います。
yaṁ hi na vyathayantyētē puruśaṁ puruśarṣabha
samaduḥkhasukhaṁ dhīraṁ sō ’mṛtatvāya kalpatēǁ 15 ǁ
暑さ、寒さ、その他の二元性に悩まされず、喜びや悲しみの間に平衡を保つ賢者(永続するものから無常なものを識別する人)は、解放に値する。
アルジュナは繰り返し「シュレーヤス」(解放)を求め、親族を殺すことでそれを奪われると言っていました。そこでクリシュナは明確に言います。「戦いから逃げてもシュレーヤスは得られない。何がシュレーヤスを与えるのか? どうすればそれが得られるのか?」聞きなさい。
ディラとは、戦争で戦ったり、戦いから逃げたりする人ではありません。私たちのシャーストラは、喜びと悲しみの平衡が取れている人(喜びのときに興奮したり、悲しみのときに落ち込んだりしない人)がディラであると述べています。
二元性は、彼の永遠の真我に対する絶え間ない認識を揺るがすことはできません。永遠の真我に対する認識に揺るぎなく、二元性を辛抱強く耐える人は、解放を得るでしょう。
nāsatō vidyatē bhāvaḥ nābhāvō vidyatē sataḥ
ubhayōrapi dṛṣṭō ’ntaḥ tvanayōs tattvadarśibhiḥǁ 16 ǁ
非現実のものは決して存在することはできない。現実のものは決して存在しなくなることはない。この2つに関する真実は、タットヴァ・ヴェッタで見ることができる。
「サット」は永遠で真実のものを意味します。 「アサット」とは、無常で非真実ものを意味します。
存在しないものは決して存在できません。存在するものは決して存在しなくなることはありません。この知識は「ニッティヤーニッティヤ・ヴァストゥ・ヴィヴェーカ」として知られています。二元性とその原因は実際には存在しません。存在しないものが存在することはあり得ますか?
「これは熱い」、「あれは冷たい」これを証明できる「実在の対象」はありません。なぜなら、熱と冷たさは単なる変容、または絶え間ない変化だからです。
土鍋は粘土に他なりません。したがって、粘土は実在し、鍋は非実在です。粘土は原因であり、鍋はその変容です。変容した物体 (カーリヤ) はその原因 (カーラナ) と異なることはできないため、非実在です。原因 (カーラナ) だけが実在します。破壊されると、創造された物体 (カーリヤ) は存在しなくなりますが、その原因は存在し続けます。
認識が変わらないものは「サット」です。認識が変わるものはアサットです。
物体を鍋や布などに分類する知性にとって、物体は非実在(アサット)であり、変化の対象です。
知性にとって自己の認識は不変であるため、実在(サット)です。「存在」はそのままです。これには変化はありません。身体が経験する二重性とその原因はアサットです。自己はどこにでも安定して存在するため、存在しない可能性はありません。これが、現実を認識した人々によって「自己と非自己」(アートマ-アナートマ)と「実在と非実在」(サット-アサット)が決定された方法です。
「実在は常に存在する。存在しないものは存在しない」。
「タット」は「すべて」を意味します。すべてはパラマートマです。パラマートマについての真の認識を持つことは「タットヴァ」です。この認識を持つ人は「タットヴァ ダルシ」です。